| トップ>住宅、建築ギャラリー>生きたバリアフリー>インテリアその2 |
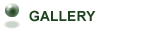 私たちがこれまでに設計し現場監理をしてきた住宅や建築を紹介します。 私たちがこれまでに設計し現場監理をしてきた住宅や建築を紹介します。
|
|
生きたバリアフリー
|

~内陣・須弥壇を見る~
宮殿(中央黒漆)や荘厳(両側)の掛け軸、輪灯(天井から下がってるV型の物)等の製作・設置は
京仏具の小掘様がおこないました。
部屋は多くの人が入るため圧迫感を感じさせないように天井をできるだけ高くしています。
メインの照明はスポットライトとすることで全体の雰囲気をすっきりさせています。
また天井の間接照明をより強調させる目的もあります。
|

~落慶法要の準備~
本堂落慶法要の準備で椅子など並べられた所です。
従来のように畳の上へ座らないで椅子に腰掛ける形になるので門徒さんにも少なからず
戸惑いがあるのかもしれませんが足の弱い方には快適にすごせるでよう。
|

~脇から眺めた内陣~
現代的な明るい雰囲気でありながら、伝統的で荘厳なイメージも共存しているようにする方法を
試行錯誤しながら出てきたアイデアが天井部分の間接照明です。
従来の外陣空間には大きな柱や梁があり空間の雰囲気を絞める役目をしていましたが、
これに代わるのが入り口から宮殿に連なるこの間接照明です。
「阿弥陀如来様」の収まる宮殿がお堂内の求心力を高める役目も担ってはいないでしょうか。
|

~須弥壇から眺めた外陣~
阿弥陀様は宮殿にはいらっしゃいませんので失礼して、阿弥陀様の視線よりやや下方よりの位置から
外陣方向を眺めてみました。
当初のプランでは、外陣へ入る引き戸中央の柱は独立して間接照明部分に
刺さるように描かれていました。
間接照明の白い光った部分が天とすると、天へ上るように不安定に細く繋がったイメージです。
これは残念ながら現世の理屈が許してくれませんでした?!
当然のことながら、トーメーの部材であっても物がある以上は枠が必要だからです。
|

~天井の間接照明~
画像がたまたま間接照明を強調した状態で写っていますが、期せずして幻想的に見えています。
玄関から須弥壇に向けて天井を貫き奥行きを強調できるように意図していました。
玄関に立ったときに阿弥陀様までの距離が実際寸法より遠く感じられるように、
照明の中央で絞りを入れてあります。
その絞り込んだ位置付近に直交するように竜骨(大工さんが名付けていました)のように
下方に反りの入った化粧材は、その距離感をさらに強調する意味も持たせてあり、
空間の雰囲気を引き締めています。
|

~洋室~
洋室から外陣をみています。
本堂は個人で参拝するなら外陣しか使いませんが大きな行事の際には
全ての部屋を同時に使用するようです。
どんな設計のプロでも使い方や動き方(動線)を100パーセント理解できないでしょう。
それはおおよその予想はできても、個人差があり、また用途によって様々に変化するからです。
したがって建築主との打合せはとても重要になってきます。
ここでも良く見られる4枚の引き違いではなく、よりオープンに使えるように4枚引き戸にしています。
又、和室でも2枚の引き違いの所を引分け戸としさらに4枚にする事で、
より広くオープンに使用できるようにしました。
建築主さんの「こんな事をしたい」からより使いやすく、時にはアイデアを提案し、デザインする・・・
そんな二人三脚な設計がとても大切です。
|

~洋室から回廊と渡り廊下を臨む~
洋室は報恩講、永代経など、寺の行事では事務所のような役割をする空間ですが、
外陣内陣と連なるひとつのおおきな祈りの場として、特に仕上げや高さを区別することはしてありません。
従来の寺院にみられた近づきがたい空間で自ずと手を合わせ祈る効果があるのは、
誰もが知る伝統的な部材で建物全体を包み込むという手法を疑いもせず繰り返した結果、
記憶に焼き付いているという単純な理由によるのみで、「なぜそんな形をしているの」と問われれば
「昔からそうだから」としか答えられないシンプルさです。
どの時代も建物の大きさや資金力でその威厳を表現してきたという極めて人間的な
発想でしかないように思えてならない。
釈迦の時代のインドやネパールではそれ以降の時代の贅沢な大伽藍など想像もしていなかっただろう。
阿弥陀様がおられればそれが寺であるという気持ちを持てば須弥壇以外の空間は全てが
祈りの空間であると思えてくるのは間違いでしょうか。
そんな思いで広く自由で明るい空間を想像しつつ現場を眺めていました。
|

~洋室から和室の方向~
洋室の西には僧侶の控えの間にもなる和室が繋がっています。
洋室と和室も開放して繋がった広間としての用途を描いていました。
法恩講など寺としての行事だけでなく、檀家の法事や広くは仏式の結婚式にも利用できないだろうか。
最近の意外と質素な婚礼事情や風潮を見ていると、隠れたスポットになりえないだろうか。
寺の行事の受付スペースというより、結婚式の控えの間としての明るい雰囲気も持ち合わせています。
|