| トップ>住宅、建築ギャラリー>生きたバリアフリー>インテリアその3 |
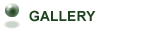 私たちがこれまでに設計し現場監理をしてきた住宅や建築を紹介します。 私たちがこれまでに設計し現場監理をしてきた住宅や建築を紹介します。
|
|
生きたバリアフリー
|

~和室~
洋室側より見ています。
この和室の畳をみると縁(へり)がない事に気が付きます。
もちろん忘れているわけでもなく意匠的にすっきりさせたかったので縁(へり)無しとして提案しました。
床の間もシンプルなデザインで統一し、タレ壁も曲線を用いることで柔らかさをだしています。
左上に濃い茶色のものがあります。
大きさは違いますがこれも先の項でお話しした紅梁(こうりょう)なんです。
やはり以前の本堂に使われていたものですが、向拝のように化粧梁としてではなく
飾りとしているため梁で彫のある部分をスライスして取り付けてあります。
和室には大きさの違う紅梁が計2箇所に取り付けられています。
奥様曰く「設計事務所さんらし配慮ですね」とのこと
|

~和室 雪見障子~
和室の雪見障子より外のストーンサークルを望むことができます。
奥に見えるのは庫裡の書院部分で法要等の時に使用される部屋で書院からも中庭を一望できます。
冬の雪の積もった情景を想像すると楽しみでなりません。
|

~和室 雪見障子~
和室の雪見障子より外のストーンサークルを望むことができます。
奥に見えるのは庫裡の書院部分で法要等の時に使用される部屋で書院からも中庭を一望できます。
冬の雪の積もった情景を想像すると楽しみでなりません。
|

~南面の廊下(回廊)~
南面の廊下は住宅の縁側のような位置にあるため陽が差込んできます。
平面計画の定石のひとつに人が回遊するようなプランにすると使いやすいということを言われます。
廊下が外陣内陣を囲むように配置されているのが伝統的な平面構成である寺の本堂ではそれが
古来より自然に取り入れられていたのですが、特に南面ではどれだけ庇を長くしても日光の
直射は避けようもなく、内陣と外陣内部の日光の差込まない一定の明るさによる落ち着いた雰囲気は、
この廊下の存在に支えられている。これは意外と大切な要素です。
|

~回廊西~
本堂は内陣・外陣、洋室、和室を回遊するように廊下が配置られその一部には収納のためのスペースを
配置しています。
お寺も様々な行事を行う上でそれ相応の『アイテム』が必要になります。
そこで回廊の一辺、約13mに渡り棚を設けました。
机や椅子、その他種類も大きさも様々ですから当然、可動棚とし天井高も高いので
いっぱいまで利用できるようにしてあります。
又、棚の一部は本堂の扉から見えてしまうため、目隠しに天井からロールスクリーンで
隠すこともできます。
ちなみにこの画像を撮影した頃は本堂落慶に向けて着々と準備が進行されていましが、
すでに棚は一杯になっていました。
|

~渡り廊下~
渡廊下にもユニバーサルデザインから床の段差も当然ですがありませんし手摺も取り付けています。
天井は船底(ふなぞこ)天井※8とすることでより広く見せ、構造梁を化粧とすることで
落ち着いた雰囲気をだしています。
又、照明も二つの角度を自由に決められる物を採用することで天井と足元の両方を照らすことができ、
天井を照射することでより広がりと幻想的な雰囲気を、床を照らすことで
足元の明確さを両立できています。
※8 船底天井・・・天井の形式の一つで、断面が船の底のように弓形や屋形になっているもの。
中央部が両端より高く、勾配を持った天井。和風天井に多く見られる形。もちろん洋風でも用いられる
|

~庫裡への渡り廊下~
寺の本堂への渡り廊下にどのような印象をお持ちでしょうか。
なぜか永平寺の渡り廊下のような修行僧が走り抜ける冷たくつらいイメージがわいてきてしまいます。
それは空間と空間を繋ぐことのみが存在価値であると言わんばかりに
軽視してしまっているからではないでしょうか。
修行という想像を超える宗教上の意味も知らずに、こんな明るいリズミカルな渡り廊下に変えてしまって
良かったのだろうかとさえ思えますが、親近感を持たせるという意味においては重要な渡り廊下です。
ちなみに廊下のクロスのテクスチャはこの画像から想像出来ないのですが、
布のような暖かさを感じさせてくれています。
|

~法中玄関-内部~
外部から見た法中玄関は控えめに渡り廊下と一体的なデザインとしていましたが
内部では風格を出すため天井部分で、桧の化粧タルキと桧の化粧野地板を見せるようにしています。
土間は当初の設計ではメンテナンス性にも優れているタイル貼りとしていましたが、
施工中に奥様の希望で『たたき土間風』※9に変更しました。
伝統的なたたき土間は無理ですからモルタルを使用した工業製品を使用しています。
視覚的にも黒い土間は品を高めてくれていまし個人的にはとても好きですね。
ただ、汚れが目立ちやすく掃除もこまめに行う必要もあり多少の色ムラもでてきます。
ここでは頻度も少ないですからデザインを優先にしています。
何にでも言えることですが、プラス面もあればマイナス面もあります。
どちらが自分にとって優先順位が上かを考えながらデザインを考える事も時には必要です。
ちなみに、たたき土間では付近の土を混ぜる事で汚れを目立たなくする知恵もあります。
※9 たたき土間・・・土と消石灰を混ぜた中に『にがり』を入れたものをたたきながら仕上た土間。
|