| トップ>住宅、建築ギャラリー>生きたバリアフリー |
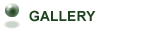 私たちがこれまでに設計し現場監理をしてきた住宅や建築を紹介します。 私たちがこれまでに設計し現場監理をしてきた住宅や建築を紹介します。
|
|
生きたバリアフリー
|
建築ジャーナル掲載
|
現代感覚の本堂を創りたい」というご住職の発想から始まったこの計画には
「生きたバリヤフリー」という言葉が似合う。
本来の心の拠り所としての本堂は、まず心身共に楽な気持ちで入ってゆけるようにすることが必要で、
それを満たすためには第一に健常者もそうでない人も楽に歩を進めてこられる設備であること、
第二に暑さや寒さを感じないそして明るい室内室内環境を創ること、
第三にはやはり阿弥陀如来の優しさに心をゆだね崇高な気持ちをもてる空間であることです。
それらを実現するために、様々な検討と工夫を凝らし試行錯誤の末、完成した。
それぞれの画像に付けられたコメントは技術的な説明にとどまらず、現場での雑感や
思い入れまで書き込んであります。
岐阜県の福祉関連ホームページに文章を投稿して掲載されたりもしました。
一度読んでみてください。
|

~参道より本堂を臨む~
参道に立って撮影してみました・・きっと一目見てお寺さんとわかる人は少ないかもしれません。
特徴的な屋根の形は基本形を『方形造り(ほうぎょうづくり)』(※3) としています。
社寺仏閣では当然のように『反り(そり)』※4 や『照り(てり)』※5 が使われています。
一般的には反りの方が多いようです。
この明秀寺では『反り』と『照り』の相反する状態を融合させています。つまり喜怒哀楽でしょうか。
骨組みはムク材(※5)を使用する木造としていますから、屋根の曲線には
今までの経験や日頃の研究から様々な工夫をもりこんでいます。
デザイン的にもタルキの曲がる範囲での屋根のラインを何度もパースにて検討を加え
一番美しく見えるラインを決めています。
~参道の話~
屋外で特に工夫したのは参道のデザインです。
やはり本堂あっての参道、それを念頭に置きながらデザインしました。
建物の特徴である屋根の自然な曲線に「賛同」したかような曲線、
さらに入口と向拝で広がりを持たせることで奥行きと広がりを与え、
さらに建物が重なることでさらに強調できます。
本堂への入りやすい雰囲気と目的地までの明確さによって、
参道に立った人は自然と本堂へ歩みよってしまうでしょう。
|
※3 方形造り(ほうぎょうづくり)・・・屋根の形式の一つ。
四方または八方の隅棟が屋根中央の一つの頂点に集まっているもの。
※4 反り(そり)・・・長い物の両端を持った時に重力にならって曲がった様子
・・・糸等を引っ張り少し緩めた状態
※5 照り(てり)・・・長い物の両端を持った時に重力に逆らって山なりにした状態
※6 ムク材・・・接着材等で張り合わせるなどの加工をしていない木材。
丸太から製材された木材そのもの。
|

~すべての人に優しい配慮~
在来の社寺仏閣では様々な理由からいたる所に段差があります。
しかし、ここ明秀寺ではあえて段違いを作らないように配慮しています。
それは、利用者の高齢化に伴う住職と坊守様(奥様)のコンセプトです。
ユニバーサルデザイン(※1)によります。
参道から向拝へは段差の低い階段に加えスロープを配置、車椅子にも対応しています。
建物内部を見ても向拝と土間床との段差が100mmあるだけで他の部屋
・・内陣、外陣、居間、和室、廊下にいたるまで全ての段差をなくしています。
・・・この考え方は廊下や入口の手摺、建具の把手(とって)等、
随所に盛り込まれています。
|
※1 ユニバーサルデザイン・・・障害者や高齢者、健常者の区別なく、
誰もが使いやすいように配慮されたデザインのこと。
1990年にアメリカのユニバーサルデザインセンター所長が提唱した考えで、
道具や建物・空間のデザインに取り入れられる。
|

~向拝に立つ・その1~
向拝の独立柱には紅梁(こうりょう)※2 が取り付られています。
・・少し色の違う梁(はり)のことですね・・
元々は従前の本堂の内部に使われていた欅(けやき)の梁でしたが新しい本堂を建てるにあたり、
本堂への感謝とその面影を残すことで門徒さんに親しみを持って頂き、
ゆく先々まで今まで以上に気軽に足を運んで頂けるようにと願いを込めて再利用することにしました。
ちなみに・・・上下の梁に挟まれている部材従前より使われていたもので蟇股(かえるまた)※3
といい蛙がまたを広げたような形から名づけられまたものです。
|
※2 紅梁(こうりょう)・・・社寺仏閣等で見かける彫りがされた化粧の梁(はり)のこと。
蓮の花や雲などいろいろな彫の種類がある。
※3 蟇股(かえるまた)・・・社寺建築などで、桁との間に置かれる山形の部材。
本来は上部構造の重みを支えるもの。
のちには単に装飾として、さまざまに彫刻してつけられた。
|

~向拝に立つ・その2~
スロープを登り切った正面から庫裡の玄関を臨む方向からの眺めですが、
最大寸法の車いすで参詣される方がいらっしゃっても無理なく
この位置まで到達できる様子がうかがわれます。
さらに、入り口の引き戸の引き具合や取っ手の大きさ、床のタイルのスベリや水はけまで、
材料の選定は吟味した設計者自身の勉強にもなりました。
|