| トップ>家づくりのプロセス>生きたバリアフリー>野地板、銅板葺き、蛤納め、紅梁、アイシネン |
 これまでに設計してきた住宅や建築の家づくりプロセスを紹介します。 これまでに設計してきた住宅や建築の家づくりプロセスを紹介します。
|
|
生きたバリアフリー
|

~野地板葺き~
野地板(※13)を葺き終えようやく屋根の形が見えてきました。
屋根の形状は照り(てり)と反り(そり)を融合させた形状となっているため住宅等で
多く使われている合板では曲線に対応できません。
曲面に馴染むコンニャクベニヤ(※14)も考えられますが、
夏の急激な温度上昇と冬の急激な温度低下を繰り返すので柔軟性のあるベニヤは選択肢からはずし、
古くから使用されるムクの杉板を使用している。
野地板に使用される杉板は間伐材から挽かれる物が多く安価で長持ちし、
幅は100mm程度と細幅のため曲面にも対応できます。
又、隅部を隅蛤納め(はまぐりおさめ)(※15)とするため隅部を丸くする必要があり、
ムク材なら自在に削る事ができる点も重要でした。
※13・・・野地板(のじいた)
屋根を葺(ふ)く下地とするために垂木(たるき)の上に張る板。
※14・・・コンニャクベニヤ(こんにゃくべにや)
風呂ふたのように一方向には柔軟性があるベニヤで任意の曲面に馴染ませることができる。
※15・・・隅蛤納め(はまぐりおさめ)
屋根の金属板葺きで四隅の処理を丸みを帯びた状態で納める工法。
材料が蛤(はまぐり)の形状に似ていることから名づけられたらしい。
|

~内部状況~
外壁に構造用合板を施工した状態の内部写真です。
天井部の梁上には屋根と同様の杉野地板が敷き詰められているのが
見えていますがはたしてなぜでしょう?・・・
これは後に施工されるイソシアヌレート系(※17)の断熱材であるアイシネン(※18)を
現場吹付けするための下地なんです。
※17・・・ウレタン変性イソシアヌレート(うれたんへんせいいそしあぬれーと)
軟質ウレタンの部類に属し熱伝導率人は0.037W/m・K
(硬質ウレタンフォーム3号:0.025W/m・K)
より劣るが、ウレタンより燃えにくい性質をもち燃え方は燻る(くすぶる)ようにガスを出しながら
黒く縮み自消する。
※18・・・アイシネン(あいしねん)
現場発泡断熱材でイソシアヌレートを主成分としフロンガスを使用しない水発泡で環境にも良い。
現場発泡のため気密を取り易いのが特徴。
透湿性がなく、不活性材で腐食の心配もなく柔軟性もあるので建物の動きに追従できる。
|

~銅板葺き~
写真は屋根の銅板葺きの様子を写したものですが茶色の部分と白っぽい部分に分かれています。
茶色の部分は銅板(純度99.97%)ですが白っぽい部分は?・・・
実はルーフィング(※19)と呼ばれるものですが、一般に使われているアスファルトルーフィング(※20)
とは異なりゴムアスルーフィング(※21)というものです。
屋根面は環境が厳しく夏と冬で温度差が50℃~60℃にもなります、
また雨漏りにも万全であることを考慮し採用しています。
最近では福岡ドームにも使われているみたいですね。
※19・・・ルーフィング(るーふぃんぐ)
屋根の防水を目的としたシート状の物で、通常は仕上げ材の下に敷かれている。
※20・・・アスファルトルーフィング(あすふぁるとるーふぃんぐ)
フェルトの両面にアスファルトを浸透させ、表面に雲母などの粉を付着させたもの。
※21・・・ゴムアスルーフィング(ごむあするーふぃんぐ)
ゴムアス防水シートとも呼ばれている。
一般には表面にゴムアス層という粘着・シール性の高い素材を使用することで釘による貫通にも
防水性が強く又、柔軟性もあり屋根の動きにも追従できる。
|

|
~隅蛤(はまぐり)部の施工~
野地板の部分でも触れましたが四方へ伸びる棟部分が隅蛤(はまぐり)納め(※15)です。
通常、目にする納まりは屋根の仕上げ面よりも15センチほど高くして金属性の水切り(※23)で
ジョイント部分にフタをするような方法ですが、
それでは屋根の柔らかな曲線に何本もの線が現れてしまうため
スッキリとした見え方にはならなかったでしょう。
この部分はデザインに大きな影響を与えるため特に意識した部分です。
完成した状態をみればそれが普通に感じられてしまうでしょうが、設計段階では頭の中や手書き、
パソコンを使い細部にいたるまでどのように見せるか、どちらがお洒落か等、
試行錯誤をくりかえしているんです。・・・こだわり抜くところは、工務店の考え方とは違う部分でしょうね。
※15・・・隅蛤納め(はまぐりおさめ)
屋根の金属板葺きで四隅の処理を丸みを帯びた状態で納める工法。
材料が蛤(はまぐり)の形状に似ていることから名づけられたらしい。
|

~通気部材~
写真は通気部材(つうきぶざい)と呼ばれているものです。
本堂の外壁と渡り廊下の屋根には近代の工法である通気層(※25)を設けています。
基礎と外壁の隙間より空気が入り外壁との隙間を通り軒裏のぶつかる部分、
又は屋根を通り屋根の棟より外部へ出ていくのが一般的です。
当然、入口と出口部分には開口がなければ空気は動けません。
しかし、この隙間にコウモリや鳥、虫が巣を作る可能性が大きいため、
進入できないようにしなくてはなりません。
そこで使用しているのがこの部材で開口部に使うことで空気は通しますが
雨水や虫などは進入できないようになっています。
これで通気層内の空気の正常な通過を保つことができるのです。
※25通気層
・・・基本は外気と通気層の温度差で通気を起こし、壁内に侵入した水蒸気を外部に逃がして
壁の中を乾いた状態に保つための層。
外壁との間の空気が絶えず動いているため断熱的にも効果が期待できる。
|

~虹梁(こうりょう)~
向拝正面(正面入り口上部)には解体した本堂の記憶を残そうと堂内外陣にありました紅梁を
加工の上再利用しました。以下にうんちくを書き並べました。
中央が上方向に起った梁の一種で、二間以上に架かった大虹梁(だいこうりょう)と小虹梁がある。
但し、小虹梁は二重虹梁と呼び、小虹梁とは呼ばない。
上に湾曲しているのは水平だと中央部が垂れて見える錯覚を是正するための工夫。
弓形に起こった形が虹を連想されることから虹梁という名がつきました。
虹梁の呼び名のほかに「月梁(げつりょう)、曲梁(きょくりょう)、
([亡]の下に[木]瘤(ぼうりゅ)とも呼ばれた。
現存する最古の虹梁は法隆寺西院のもので飛鳥様式をそなえた奈良時代の建築。
虹梁は構造的には梁と同じく屋根や天井の荷重を受けたり母屋と庇を繋ぐ役割を果たしている。
虹梁は位置や形状あるいは大小によって分類名前が付けられているが、
一般的には「大虹梁(大きな虹梁の意味にも使うが二重虹梁と重ねて使ったときの
下の大きな虹梁(その両端は身舎柱(もやばしら)に架かる)のことを指す)、
二重虹梁(大虹梁と重ねて使う時の上の小さな虹梁のことで長さは大虹梁の半分)、
繋虹梁(高さの違う柱(架構の一端は柱の上、他端は柱の中腹に来るように配される)をつなぐ)、
海老虹梁(S字型の虹梁で両端の高低差が著しい場合に用いられる
(鎌倉時代に禅宗様として導入された円覚寺舎利殿外陣が早い例))、
水引虹梁(向拝の正面に使われる)」などがある。
虹梁に装飾が施されるようになったのは鎌倉時代に入ってからだそうです。
|
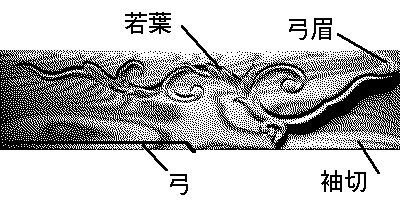
眉(まゆ) 虹梁の下端近くを一条ないし数条の平行線でえぐったもの。眉を欠くという。
袖切(そでぎり)虹梁が柱より太いとき、柱に取りつく部分の両側を斜めに欠き取った部分。
弓眉(ゆみまゆ)袖切の境の眉のこと。
鯖尻(さばじり)柱に取りつく付近の上部の弧形の部分。
虹梁鼻(こうりょう)虹梁の柱より外に出た部分のこと。
若葉(わかば)虹梁の側面に施された唐草などの彫刻をいう。
錫杖彫(しゃくじょうぼり)虹梁の下端に施した彫り込みをいう。
|

~アイシネンの施工~
内部写真の部分で少しふれましたアイシネンの施工が完了したところです。
断熱材の厚さは100mm(実際は柱の幅ですから120mm相当ですが)白い部分がそうです。
少し見えにくいですが天井の梁上にも白っぽいラインが見えているでしょう?
この部分も小屋裏側からアイシネンを吹付けていますから天井断熱(※26)になります。
泡のように転々とあるものもアイシネンですがあれはなぜ丸くなっているのでしょう?
よくみると斜めの部材の端部にみられますよね!?
これは火打梁(ひうちばり)(※27)と呼ばれるものでそれを梁・桁(はりけた)と固定するために
六角ボルト(※28)が使われています、
この部分は外部の空気と接触しているために高気密高断熱の建物で注意しなければならない
ヒートブリッジ(熱橋:ねっきょう)(※29)となる可能性が高いため
アイシネンで被覆(ひふく)しているんです。
※26・・・天井断熱(てんじょうだんねつ)
天井の仕上げ材の裏側、又は梁の上端部で断熱材を施工する工法。
屋根で断熱する方法もありその場合は屋根断熱という。
※27・・・火打梁(ひうちばり)
梁や胴差し(どうさし)又は小屋組等で斜めに入れる部材。
地震動や風圧による建物の変形を防ぐ。
※28・・・六角ボルト(ろっかくぼると)
ネジが切られた鋼棒に六角ナットと座金を使って材料をで締め付ける金具
※29・・・ヒートブリッジ(熱橋:ねっきょう)
断熱された建物の外壁などに、部分的に熱を伝えやすい物や状態があるとその部分から
橋を渡るように熱が出入りすることからこのような名前が付いた。
熱伝導率は木材(乾):0.16W/m・K コンクリート:1.0W/m・K
鉄:83.5W/m・Kと比較すると鉄が熱を伝え易いことがわかる。
|