| トップ>住宅、建築ギャラリー>数寄に住まう |
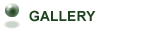 私たちがこれまでに設計し現場監理をしてきた住宅や建築を紹介します。 私たちがこれまでに設計し現場監理をしてきた住宅や建築を紹介します。
|
|
数寄に住まう
|

生活の中心、居間
居間南,テラスのサッシから北側のダイニングのサッシに直線で通風が確保できる、
まさに家の中心部にあります。
画像に見えているのは、その北側のサッシとダイニング脇の和室の個室、洗面所の入り口、
下の画像はキッチンのカウンター、玄関ホールへの扉と
そして建築主さんのパソコンデスク兼本棚プラスデスクの造り付け家具です。
天井が高くなっているのはトップライトのある場所です、
生活の基本動作はここで全て完結してしまうということになります。
広い部屋になっていますから冬の寒気や暑さで不快な思いが避けれるようにと、
高断熱高気密の温度差の無い空間になっています。

|

居間のトップライト・テラスのような居間
画像には居間の南にあるテラスが一部しか写っていませんが、
トップライトは南の屋根に取り付いており居間全体を明るく照らしています。
ご覧のような大きさですから昼間は照明が必要ありません、
それが自慢できることかとお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが
昼間でも照明をつけている方は意外と多いのではないでしょうか?
3.11東日本大震災以来の節電ムードとは関係なく、
以前よりユニバーサルデザインの立場から昼間はせめて太陽の明るさを室内に取り込む、
(ただし熱は取り込まない工夫をしていますが)
室内のそこかしこから外部の明るさや気配を取り込むことをしてきたつもりです。
南の庭園へとテラスを介してつなっがっている、
庭園を趣味でいじったり眺めたりという以前からの習慣を今後も続けたいという
建築主さんの要望からしても外部のような明るさはその連続性が「テラスのような居間」
と感じることが出来るのではないでしょうか。
|

ダイニングと和室
ダイニングとキッチンの西側の和室は引き戸を全て引き込むと
オープンなワンルームになるようになっています。
居間という多目的な空間の一部にたたみ敷きの空間を設けておくのは、
座っての食事で寛いだり、予備の個室を用意しておきたいという要望
を受けてのことです。
|

2階の居間
将来の2世帯同居を見越して2階にも広い居間を囲むように個室を配置しています、
南側にはベランダがそれぞれの部屋に接しており、平面図が無いので分かりにくいのですが
1階のテラスハウスのような基本形を2階にも生かしています。
北側の壁面には配管を埋め込みキッチンを設置して接続すれば使用できるように用意されています。
屋根断熱となっているためご覧のようなロフトが何箇所も出来ていますが
これらは繋がっており換気扇で強制的に排気されるようになっています。
ロフトはあえて使い方をハッキリさせてありません、たぶん子供さんの遊び場、
たぶん子供さんの部屋いや隠れ家、たぶん家財置き場、
私ならば趣味のパソコンいじりやブログ編集の隠れ家かもしれません。
そんな事情もあってロフトには自然風が入るように連窓を取り付けて
居間にも明るい昼光が刺し込むようになっています、
ただし夏の熱気は入らぬように庇を深くかぶせてあります。

|

システムキッチンはシステムにあらず
「システムキッチン」という言葉からは過去の時代にあったパーツを組み合わせるタイプには
出来なかった多くの機能を要望のままに組み込んでくれる・・・・という印象があります。
しかし現実には思う通りに100パーセントというわけにはいかないのです。
100パーセントで無いということは発注者にとっては正直なところ
「がっかり」「なんだそうだったのか」という感想になっている状況に何度と無く遭遇しています。
特にカウンターなどの家具部分との取り合いが要望のように納まらないケースは多く、
ご覧のように製作家具にて要望をまとめて組み合わせます。
この場合システムキッチンの機能はどのメーカーも充実していますので
デザインにマッチしていることが重要で、特に色などは淡色のシンプルなものがうまくいくようです。
|

オルスバーグの蓄熱暖房
「数寄に住まう」の特徴のひとつはこの暖房機です。
ドイツでは400年の歴史のあるオルスバーグ社の蓄熱式の暖房機、
オール電化契約の深夜電力を利用して蓄熱した熱を昼間にも使用できる仕組みになっていて
その経済性を発揮してくれます。
冬の厳しい北陸育ちの建築主さんが製品の魅力を知っておられたことで採用の機会に恵まれました、
竣工後の使い心地も良かったようで、部屋全体をゆったり暖めてくれてエアコンのように
風を感じることも無く、気密断熱施工により上下の温度差を感じることもないようです。
まさに健康に良い機器ではないでしょうか。
|

寝室の位置
住宅を新築する際にはバリアフリーやユニバーサルデザインの考え方をベースに作ることは
すでに常識化しています。
段差の解消、廊下や階段の巾の拡幅、廊下階段の手すり設置、出入り口の拡幅や引き戸化、
部分の改善だけにとどまらず、視力低下を補う明るい内装や足元照明や火災警報器の設置など、
設備の工夫や室内温度差の解消のための断熱化など建物の壁や屋根、
開口部の構造も大きく影響を受けてきました。
「数寄に住まう」ではさらに平面計画の基本もバリアフリーの考え方を反映させました。
とはいうものの目新しいことではなく誰もが自然発生的に思いつくことで、
生活の中心を囲むようにダイニングや洗面、トイレ、個室、浴室、全てをストレス無く
アクセスできる平面計画やディテールを工夫したということです。
寝室は南の庭を望める位置ですが、ウォーキングクローゼットや居間は直接アクセス、
トイレや洗面ユニットバス、キッチン、ダイニングは居間を通じてアクセスできるようになっています。
住み始めればごく当たり前に習慣化するであろう便利さですが、
あえて設計時点から取り入れなければ実現しないのも平面計画のバリアフリーです。

|